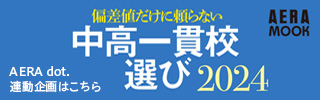京都大学 分野別講義
SSH学校の様子高2
5時間目と6時間目に京都大学の8名の先生に分野別講義をしていただきました。
高校2年生の生徒全員が、理系3・文系5の計8講義から事前に興味のある2つの分野を「理系・文系」の選択に関係なく自由に選んで受講しました。

赤松 明彦 先生 (哲学)
「世界と魂と『私』?人間は何を考えてきたか?」
「世界と魂と『私』?人間は何を考えてきたか?」

天野 恭子 先生(古代インド文献学)
「古代言語解読の方法と文献研究の広がり」
「古代言語解読の方法と文献研究の広がり」

檜山 智美 先生(西域仏教美術・シルクロード文化史)
「シルクロードの仏教美術史:
絵画から読み解く文化の歴史」
「シルクロードの仏教美術史:
絵画から読み解く文化の歴史」

藤原 敬介 先生(言語学)
「五十音図の謎ー「あいうえお」から「ABC」まで」
「五十音図の謎ー「あいうえお」から「ABC」まで」

中井 愛子 先生(国際法)
「国際法の世界・世界の国際法」
「国際法の世界・世界の国際法」

門 信一郎 先生(プラズマ科学・核融合科学)
「真空放電が拓いたプラズマと量子の世界」
「真空放電が拓いたプラズマと量子の世界」

潮 雅之 先生(生態学)
「森や海から自然の法則を見つけるための科学の方法」
「森や海から自然の法則を見つけるための科学の方法」

瀧川 晶 先生(宇宙鉱物学)
「宇宙鉱物学への招待
~原子の世界から宇宙のどこかまで~」
「宇宙鉱物学への招待
~原子の世界から宇宙のどこかまで~」
2コマの講義終了後、自分の教室に戻った生徒の「どの講義受けた?めちゃくちゃ良かった!」「私も~!もっと聞きたかった!」という会話が聞こえてきました。
専門の講義に加え、先生ご自身が研究者になるまでのお話などもあり、自分の未来を想像する機会にもなったようです。
50分という短時間で研究への情熱と可能性を高校生にもわかりやすく講義して下さった京都大学の先生方、本当にありがとうございました。